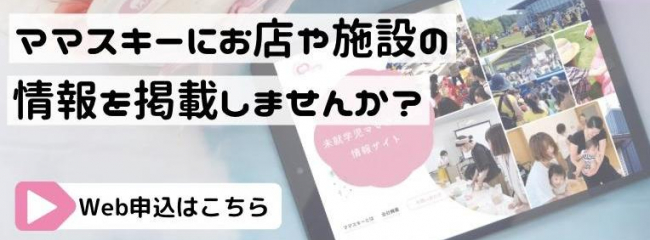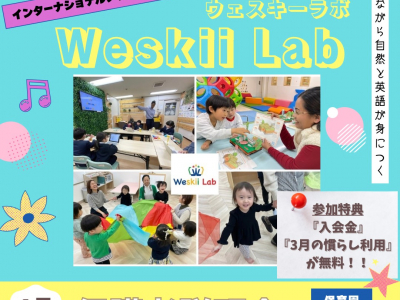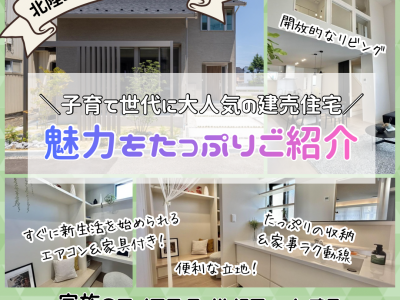東京で2児を育てているママスキーキャストのFです。
いよいよ始まった、夫の1年間の育休。
1人目と2人目の育休との違いは?どんな生活だった?
そんなことを振り返って書いていきたいと思います。
一人目と二人目の育休の違い
一人目の育休と、それ以降の育休では、違ったメリットがあると思っています。
一人目の場合、夫婦ともに初めての子育てで不安が多いので、二人で支えあって子どもを育てていくという意識づくりのため、そしてママの心身(特に心)の負担軽減のためにも、男性育休は是非取って頂きたいと思っています。
この度二人目の男性育休を取得して、同じく是非取って欲しいと思ったのですが、その大きな理由が「上の子のケア」です。ほとんどの子が赤ちゃん返りをします。自分だけに構って欲しい、ママを独り占めしたい、下の子のために遊びを我慢したくない、等、それまでとの環境や状況の変化に対応するまで大きな戸惑いがあり、パパやママも手を焼くことになります。自宅保育の家庭でワンオペの場合は、上の子に我慢をさせてしまう場面がどうしても多くなりやすいです。まだまだ気持ちの整理がつかない時期なので、上の子のためにも育休を取ると穏やかに過ごしやすいと思います。
実際、我が家の場合はパパがほぼ上の子につきっきりでした。パパばかりになってしまわないように、私も授乳のタイミングを見ながら上の子と二人で遊びに行く時間を作ったりもしました。自治体の助成が出るので下の子も生後1か月からシッターさんに何度か保育をお願いしていて、パパとママと上の子の3人でお出かけをしたことも。遠慮なく両親に甘えられる時間があったことでケアもできたし、私にとっても貴重な時間でした。
経済的な不安をもつパパママへ
いくらメリットを語られても、生活にはお金がかかるんだから働かないと不安…という方も多いでしょう。育休手当って実際どのくらいもらえるの?というのも気になると思います。育休手当に関しては住んでいる自治体や会社によって制度が違う場合もあり、日々変化していっています。なので、あくまでこれは我が家の場合であり、都度会社や行政に確認はしていただきたいのですが。
まず、育休取得前にやって置いて欲しいことのひとつは、「有休消化」です。うちの夫は1年間の育休を取得しました。厳密にいうと、出産前の管理入院の期間に数日有給休暇、出産から3日間は特別休暇が支給、その後1歳の誕生日当日まで育休でした。間に年度が変わっています。年度が変わると、消えてしまう有給休暇とまた与えられる有給があるので、まずは消えてしまう有給休暇を出来るだけ消化して家族の時間を作ったり出産に向けての準備をしたり、ママの身体を休ませてあげたりしてください。早く使い切ってしまってもいざというときに取れないので、難しいとは思いますが計画的に。
そして育休手当について。育休が始まると、育休手当は2ヶ月分をまとめて、さらに翌月に振り込まれました。はじめの6ヶ月は基本給の67%、その後の6ヶ月は基本給の50%です。このように聞くとかなり収入が下がるように思いますが、これらは非課税です。だいたい、基本給の67%の時点でいつもの手取りとそんなに変わらない程度になっているのではないでしょうか。残業代やボーナスがないので働いているときよりもプラスになるということはありませんが、家族の時間に集中できる状況=忙しいときにはお金で解決してしまっていたことを自分でできるようになるので、支出は減りました。
夫の話ばかりになっていますが、ママである私は産後3ヶ月で復職しました。これは、私は休職しても手当が出ないアルバイトであるということ、復職しても週3日程度の勤務で在宅作業も多いことから、復職することを決めました。上の子が就園するまでは託児所を利用することもあり、経済的にも体力的にも夫婦で無理のない範囲でやりくりしていました。
収入が少なくなる時期ではありますが、せっかく時間はあるので旅行は行きました。復職したら行きにくくなるような長めの旅程も、奮発して。そのかわり、オフシーズンの平日だけで組めるので旅費も安く、旅先も空いていて快適に過ごせます。育休前は定期的に旅行していましたが、育休中に少し詰め込んで、復職後はしばらく我慢するつもりです。どの旅行もとっても良い思い出になりました!
2024年末に家計簿でざっと確認。もちろん所得はかなり減った1年でしたが、その分支出もかなり抑えられました。
一人目育休のときには株の勉強をして実際に株を始めました。今も子育てや生活に役立つ株主優待をうまく活用して、無理のない節約生活を楽しんでいます♪
お金の不安は少し解消されましたか?
次回は、なにかと揉めがち?炎上しがち?な、家事育児の「分担」についてです。
その3に続く…